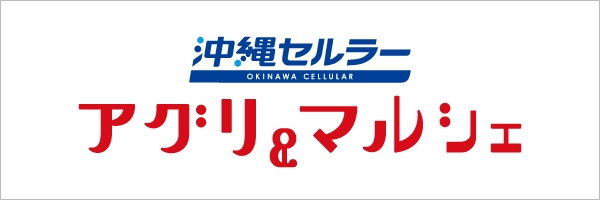三線文化を守り伝える《沖縄県三線製作事業協同組合》
三線文化を守り伝える《沖縄県三線製作事業協同組合》
Reading Material
歴史文化
放送日:2025.09.29 ~2025.10.03
初回投稿日:2025.10.06
最終更新日:2025.10.06
最終更新日:2025.10.06
沖縄の伝統芸能に欠かせない「三線」は、それ自体が重要な沖縄文化のひとつであり、三線づくりもまた、後世に継承すべき技術といえます。しかし、近年は職人の高齢化、原材料の枯渇、安い海外産品の増加など、さまざまな問題が山積しているのも事実。そうした問題に組織として立ち向かうべく、三線職人が集まって2010年に設立したのが「沖縄県三線製作事業協同組合(以下、組合)」です。
目次
個人では対処できない問題に組合で取り組む
組合の設立は2010年ですが、その構想が最初に立ち上がったのは、さらに30年以上前のこと。1973年にワシントンDCで採択された、絶滅のおそれがある野生動物の保護を目的としたワシントン条約の影響で、「三線の胴に使うニシキヘビの皮が輸入できなくなるかもしれない」という問題が浮上し、職人の間に危機感が広がりました。そのとき「一人では何もできないが、みんなで集まって組合を作ったら何かできるのでは」との話になり、組合の準備委員会が作られたのです。
ただ、結果的にこのとき、蛇皮の問題は大事には至らなかったため、組合構想はいったん立ち消えになりました。

三線の胴に張られているのはニシキヘビの皮。主に東南アジアから輸入されています
しかしその後、前述の後継者不足や材料の枯渇、外国産の三線の増加など、三線を取り巻くさまざまな問題がどんどん顕在化。組合の必要性が改めて議論されるようになり、2010年に「沖縄県三線製作事業協同組合」が設立されました。
現在は、組合店舗での三線の展示や販売をはじめ、新商品の開発や販路拡大、三線の魅力を伝えるための三線教室やイベントの実施、三線の棹の原料となるクルチ(黒木=黒檀)の植林・造林など、三線作りの技術を次世代につなぐためのさまざまな取り組みを行っています。
組合から生まれた新たなつながり
理事長の渡慶次道政さんは、現在の組合について「立ち上げから15年で、まだまだ道の半ばだけど」と振り返りつつ、その未来には希望を感じていると語ります。
「自分たちはこれからも三線作りが続けられるような体制を作らないといけない。そのために組合も職人も頑張っているし、皆で一丸となって、三線の魅力を発信する活動に力を入れているので、今のところ大丈夫だと思います」

組合理事長の渡慶次道政さん。2024年、三線職人としては初めて国の伝統工芸士の認定を受けました
一方、組合の副理事長を務める岸本尚登さんは、組合を作ったことで「三線つくやー(=職人)の存在が、より広く認知されるようになった」ことを実感しています。
「これまでは三線というと、弾き手にばかり注目が集まっていたけれど、組合が活動を始めたことで、三線という楽器自体にも目が向けられるようになってきたと思います」

副理事長の岸本尚登さん。祖父から続く三線工房の三代目です
また、組合を作ったことで、各種団体や企業、アーティスト、自治体など、三線を取り巻くさまざまな関係者とつながりが生まれ、職人個人では成し得なかったプロジェクトやタイアップ企画、商品開発などにも取り組めるようになりました。
そこから生まれたのが、三線の皮に39酒造所の泡盛ラベルをデザインした「泡盛三線」や、著名な三線アーティストの意向や好みを反映して製作した「アーティストモデル三線」、そして火災で焼失した首里城と震災地・能登の復興を願い、三線職人と輪島塗の職人が協同で製作した「復興三線」などです。組合では、「これらのコラボ三線を介して、より多くの人に三線に親しんでほしい」と願っています。

県内39か所の酒造所とコラボした「泡盛三線」は、泡盛ファンにも人気です
クルチ(黒木)に代わる木材を探して
組合がコラボ三線など新たな三線作りに取り組む背景には、三線の棹の材料となる新たな木材の研究や、若手職人の育成という目的もあります。
従来、三線の棹の材料には、沖縄県産のクルチ(黒木=黒檀)が最適とされてきました。しかし現在、県産のクルチはほぼ枯渇状態にあります。県内では植樹作業も始まっていますが、クルチの木は成長が遅く、棹の材料として使えるようになるには100年以上かかるため、それまでの間は別の木材を使わざるを得ません。
コラボ三線では、棹にクルチ以外の代替材を使用し、それぞれの代替材の特徴や音色などを研究し、三線作りの可能性を広げていくことを目指しています。

「組合でもクルチの木を育てていますよ」と紹介してくれたのは、事務局の新垣恵さん。この鉢植えは3~4年経ったものだそう
そもそも一挺の三線を完成させるには、木材の調達から数えて7~8年という長い時間がかかります。木は乾燥するにつれ歪みが生じるため、まず5年ほど寝かせて様子を見、大きな変形や割れが生じていないことを確認したうえで、慎重に作業を進めていきます。しかも、岸本さん曰く「三線は『作ったら終わり』ではない」とのこと。「三線は完成から10年経っても木が歪んだりせず、ちゃんと弾ける状態にないと意味がありません。だから代替材の検証には時間がかかるんですが、この先も三線という楽器を継承していくためには、いまこの研究に取り組まなくてはならないと考えています」

三線の棹の材料となる木材は、角材の状態で5年ほど寝かせ、乾燥させます
若手職人の育成も課題の一つ
組合が直面している問題のもう一つが、後継者不足と、それに伴う若手職人の育成です。
現在、組合に加入している職人の数は十数名。組合未加入の職人を含めても、県内の三線職人の総数は20名程度に過ぎません。しかもその中心は70代で、そう遠くない将来に彼らが現役を退いたら、職人の数が激減することは目に見えています。岸本さんは「組合で取り組むべき課題はいくつもありますが、若手の育成が一番難しい」と語ります。
「昔は『自分が作った三線が売れるようになるまでの修行期間は無給』というのが当たり前でしたが、今の時代はそうもいかない。それに、以前は『入門用の比較的安価な三線作り』というのが若手職人の仕事として存在していましたが、最近は海外からもっと安い三線が入ってきていて、そうした需要も減ってしまいました。そんな中でコラボ三線は、若手職人が手がける貴重な仕事の一つになっています」
代替材の研究にしろ、若手の育成にしろ、これらは一朝一夕で解決できる問題ではありません。だからこそ組合では長期的な視点を持ち、「今できること」に地道に向き合っているのです。海外の壊れた三線を甦らせたい
組合では三線作りに加えて、三線のメンテナンスにも力を入れています。県内外のイベント等で、職人によるメンテナンス会を開催するほか、海外の県系コミュニティから来沖した留学生を受け入れ、三線の修理方法を指導する活動も続けています。

現在はアメリカからの留学生で日系2世の西菜緒美さんが、岸本さんの元で三線の修理方法を学んでいます
実は海外の県系コミュニティには、沖縄から移民した一世の人々が持ち込んだ三線がたくさんあります。それらの三線の中には、年月を経てパーツが破損し、弾けなくなったものもありますが、現地に修理できる人がいないため、多くはそのまま放置されているのだそうです。組合では、留学生に三線の修理方法を学んでもらうことで、彼らが帰国した後にそれらの三線を修理し、再び弾ける状態にできるよう、丁寧に指導を行っています。
サンシンレンジャーがつなぐ三線の未来
組合では、三線の製作や販売だけでなく、三線そのものを広く知ってもらい、愛好者を増やすための活動も積極的に進めてきました。これまでも県内外で、三線教室や三線体験会の開催、展示会への出展など、さまざまな取り組みを行っています。

組合の店舗では、三線の個別指導も行っています。オンラインで県外から受講する生徒もいるそう
その中で、2022年から始めた新プロジェクトが「サンシンレンジャー」です。サンシンレンジャーは「人々の心を美しい音色で癒し、この島でいつまでも三線の音色が響き続けること」を目指して、武器ではなく三線を手に活躍するヒーロー。このキャラクター誕生の背景には、組合メンバーの「子どもたちにも、三線に興味を持ってもらいたい」という願いがありました。事務局の新垣さんは語ります。
「子どもの頃に三線と親しむ機会を持っていたら、その中から将来は実演家になる人も出てくるかもしれないし、そうでなくても、大人になってから『また三線をやってみようかな』と思う人もいるかもしれない。サンシンレンジャーを通じて、子どもたちにそうした三線との出合いを作っていけたらと思いました」

イベントでサンシンレンジャーが登場すると、子どもたちは大喜び!
三線作りからメンテナンス、三線の指導にPR活動まで。100年先、200年先まで続く三線文化の継承を目指して、組合のウェルビーイングな活動はこれからも続いていきます。
沖縄県三線製作事業協同組合
- 住所 /
- 沖縄県那覇市安里360-7 和光マンション1F
- TEL/FAX /
- 098-884-8288
- E-Mail /
- info@okinawa34.jp
- Webサイト /
- https://okinawa34.jp/
- ショップサイト /
- https://ok34.shop-pro.jp/
![]() 沖縄CLIP編集部
沖縄CLIP編集部
TVアーカイブ配信中
放送日:2025.09.29 ~ 2025.10.03
-
放送日:2025.09.29
-
放送日:2025.09.30
-
放送日:2025.10.01
-
放送日:2025.10.02
-
放送日:2025.10.03